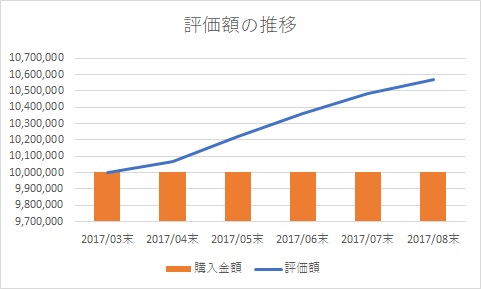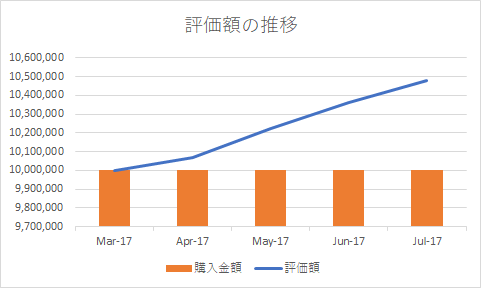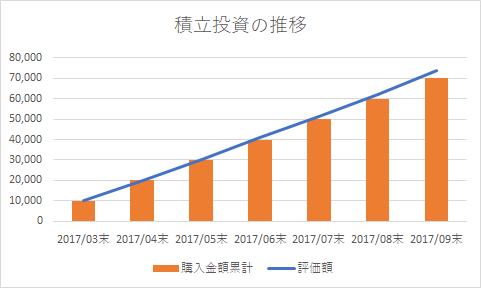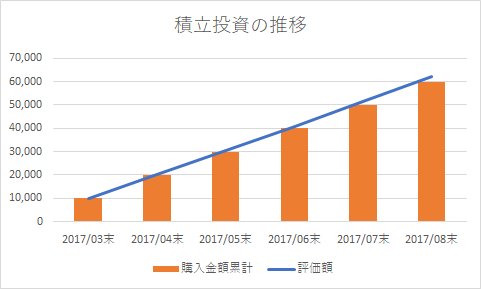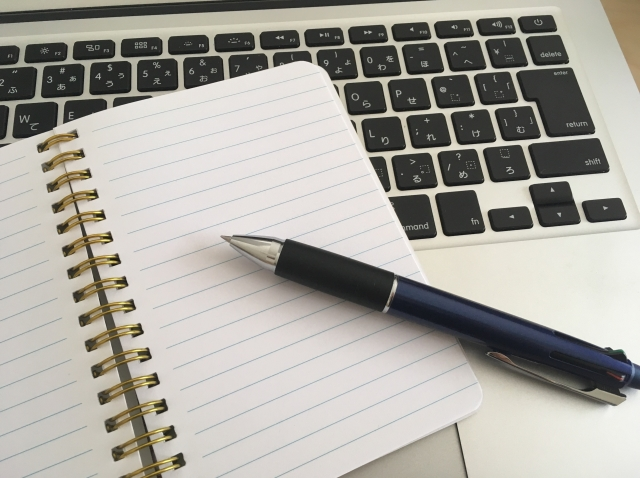2017/03/30
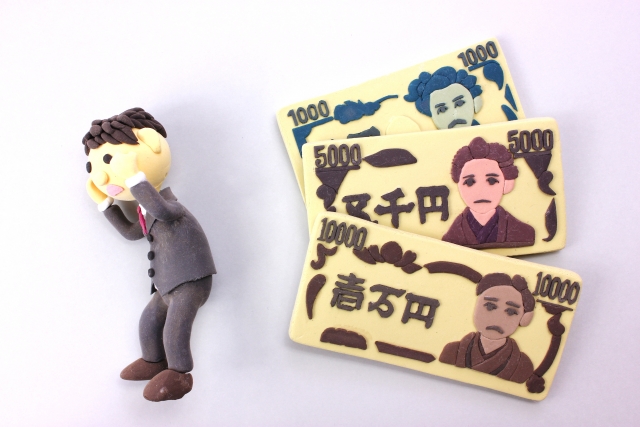
6月8日の日経新聞に、郵政「貯金頼み」転換、投信、郵便局の9割で、という記事が掲載されていました。

投信販売による手数料収入を強化し、経営の軸足を「貯蓄から投資」へと移していく、とあります。
そろそろ夏のボーナスシーズンですね。勤務先が確定拠出年金を導入したり、個人でイデコ(個人型確定拠出年金)を開始している方の中には、一般の銀行や証券会社でも投資商品の購入を検討している方もいらっしゃるかもしれません。
でもどこで買えばよいの、と迷いますよね。
この新聞記事を見て、郵便局で相談してみよう、とお考えの方もいるかもしれません。
が、その前に銀行、証券会社、郵便局、ネット証券、などの特徴を整理してご自身が長く続けることができる金融機関を選んでいただきたいと思います。
今回のコラムでは、投資信託等の有価証券を買えるところを整理し、ご自身が長く続けることができる購入場所を見つけるヒントにしていただきたいと思います。
お断り
筆者の個人的な経験や当社がお取引を頂いているお客様からのヒアリングによるもので客観的なデータ、調査に基づくものではありません。実際のお取引に当たっては記事を参考に必ずご自身でご確認ください。
今回は3つのポイントで整理したいと思います。
1.コスト(手数料)
2.ラインナップ
3.相談機能
1.コスト
資産運用においてはコストはとても重要なファクターになります。当サイトの考え方では、資産運用とはお金の貸し借りですから、最終的な投資先からのリターンから金融機関の手数料を引いたものが投資家のリターンになります。
コストは主に、商品そのものの手数料(投資信託の信託報酬など)と売買手数料、になります。
簡単に言えば、じっくり相談をして手のかかった商品を買えば手数料が高くなる。一方、自分で決めて自分で手続きをすれば手数料は少なくなる、ということです。
つまり、大手の金融機関で営業マンの話をじっくり聞いてお勧めの商品を買えば手数料が高くなり、ネット証券などで自分で完結すれば手数料は少なくなる、ということになります。
では、商品は自分で決めて手続きだけ大手金融機関で、はできるでしょうか?
商品は自分で選ぶが手続きは電話等、人を介して取引したい、という要望は多いと思いますし、それができれば投資家には大きなメリットがあると思います。
残念ながら多くの金融機関では、営業マンが対応する支店・部署でローコストのインデックスファンドのような商品の取り扱いをしていない、ケースが多いように感じます。
大手金融機関でもネット専用口座では、ローコストの商品を購入時の手数料ゼロで購入できますからこちらもネットでの取引が問題ないなら選択肢になると思います。
ということで、コストという観点からはネット取引ができるかどうかがポイントになりそうですね。ネット証券を上手に利用できるかどうかがコストに関しては重要ですね。
次回は2.ラインナップです。