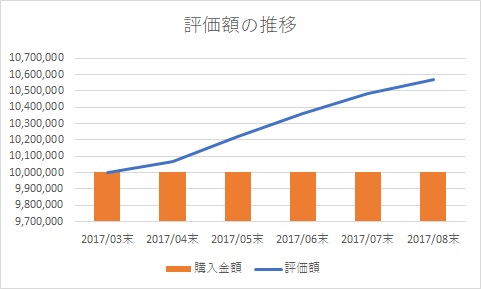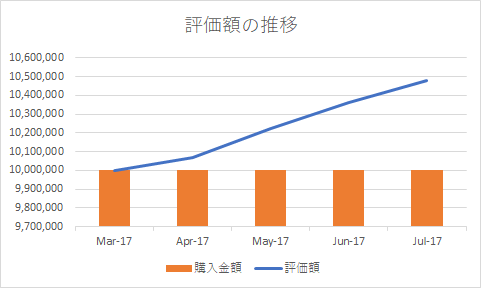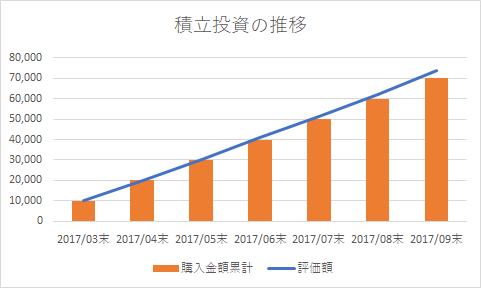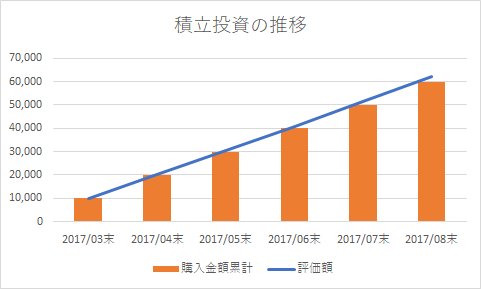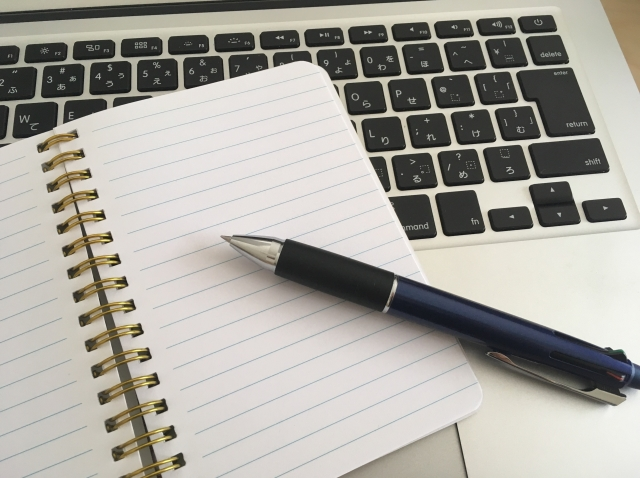2017/03/30

日経 2017年3月1日
株式や債券などの伝統的なアセットクラスの相関度が上がり、分散投資により価格変動を抑える、ということが期待しずらくなっていますよね。
そんな中、株式などの伝統的資産との相関度が低い資産クラスとしてヘッジファンドなどの代替資産が注目されています。
で、この見出し「株・債券から金・ヘッジファンドへ」になるわけですね。
一方海の向こうでは、こんな賭けが行われていました。
これは、10年間で、ヘッジファンドとSP500のどちらのパフォーマンスが良いか、仮にヘッジファンドが勝ったら100万ドルをバフェット氏が払う、というものです。
記事によると、「ヘッジファンド群の16年まで9年間の年間リターンがプラス2.2%に対し、S&P500種のインデックスファンドはプラス7.1%」
今年で勝負がつくのですが、バフェット氏の勝ちは間違いない、といわれています。
ここには詳細な分析はありませんが、おそらくヘッジファンド側の主張は、2.2%のリターンを得るのに値動きが少ない、一方SP500は、7.1%のリターンを得たが毎年大きな価格変動がある。
単にリターンのみを比べるのではなく、いかに価格変動を抑えてリターンを挙げたかに焦点を合わせるべきだ、と。これも一理ありますよね。
では、どのように考えればよいでしょうか?
前提はグローバル分散投資をする上でのアセットクラスとしてどうか、という観点からです。
当サイトの考え方を前提とするならば、
組入れるとしても1割程度、特に必要なければ組入れない。
理由
とくに調子が悪い時に継続保有するべきか、あきらめるべきかの判断をしなければなりませんが、なかなか個人の方がそれをするのは難しいのではないでしょうか?おそらく関与しているほとんどの人(ファンドマネージャーも含めて)もその判断は相当難しいのではないかと思われます。
これはブルームバーグの昨年の記事ですが、1年間の新規設定910本に対し、閉鎖が1053本と閉鎖が上回ったそうです。
それでもポートフォリオ全体のリターンを下げずに価格変動を抑えたい、ということであれば1割ぐらいなら良いように思います。1割に特に根拠はありません。
必要なければ組入れない。
ポートフォリオの価格変動を抑えるために、というのを逆から読めば、価格変動を受け入れることができれば必要ない、と読むこともできます。なので、ちょっと乱暴な表現になりますが、価格変動を避けるために訳が分からない(自分で対処できない)ものを入れるより、つらいけど価格変動を我慢したほうが長続きする、と考えるからです。
ヘッジファンドについての他の記事
世界を代表する機関投資家が全く異なった判断をしているのですね。つまり何をしたらよいか、より、これなら成果を得ることができるはずだ、という自分なりのポリシーを確立し、維持継続することが大切なのかもしれませんね。
一方エール大学はポートフォリオ全体の2割程度をヘッジファンド等にしています。ヘッジファンドのみならず全体の8割程度が代替資産ですね。
詳細はこちら(2Pです)
ヘッジファンドについてのお勧め書籍
少し古い本になりますが、伝説のヘッジファンドLTCMについてのドキュメントです。ご興味がある方にはとても面白いと思います。
勝者のポートフォリオ戦略はアメリカでも有数の基金(規模・パフォーマンス)であるエール大学の運用担当者の著書です。ヘッジファンド云々の前に規律が大切ということがよくわかります。