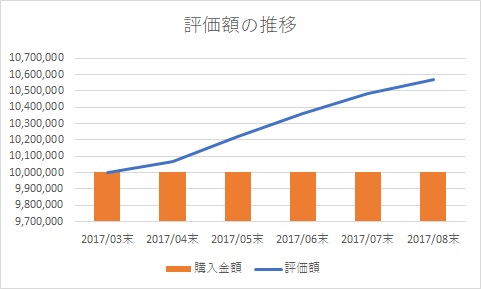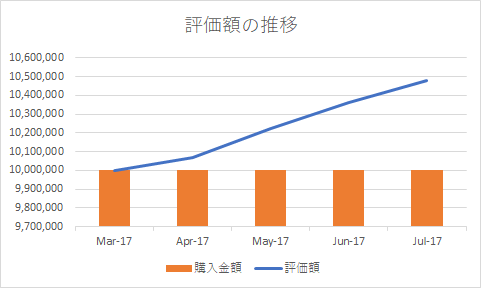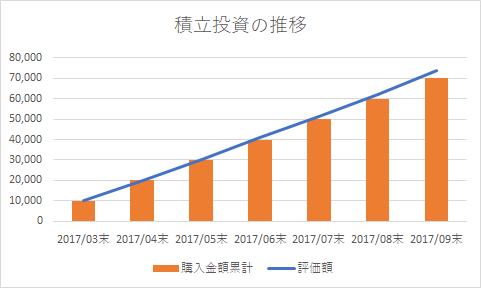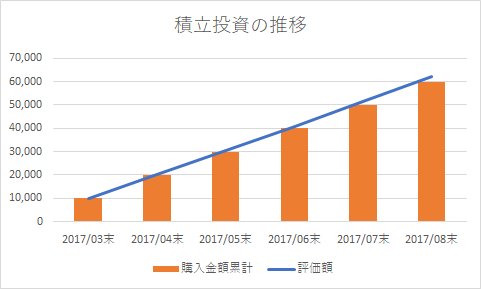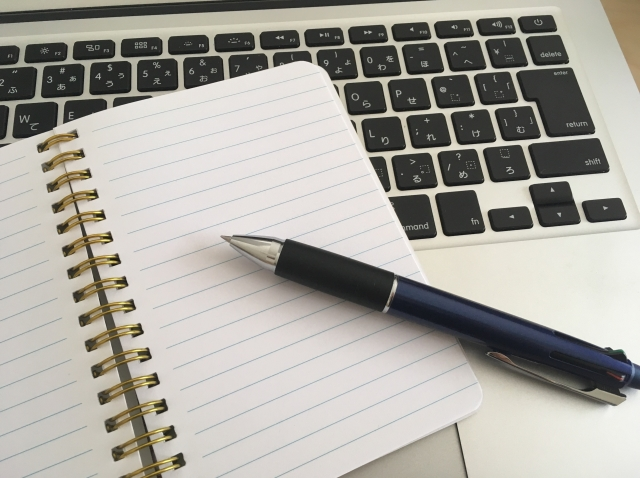2017/03/30
長期の資産運用では、
- 全体の資産配分を決める
- 各資産ごとに実際に購入する商品を決める
という手順を取ります。実際にどのような商品を選ぶかという段になったら、まずはその資産の種類(アセットクラス)にインデックスファンドがあるかどうか確認してはいかがでしょうか?
私は金融商品仲介業者として約15年に渡り個人のお客様向けにサービスを提供してきました。その中で課題に感じたのは、お客様が保有している投資信託のほぼすべてがアクティブ型の投資信託で、インデックス型の投資信託はほとんどない、ということです。
商品に内包される様々な手数料を金融機関が分け合うという仕組み上、仕方がないとは思いますが、全く選択肢として取り上げられず、金融機関がお勧めする商品を買うか買わないかの選択をし続ける投資では成果を得るのは難しいのではないでしょうか。
本来であれば金融機関の窓口などで、少し辛辣な言い方ですが、セールストークだけを覚えているような営業担当のお勧めを検討するような方こそインデックスファンドを選ぶべきだと思うのですが、どちらかと言えば金融理論に詳しい方がインデックスファンドを選び、そうでない方が通貨選択型やカバードコール戦略、などとても複雑な商品を購入しています。
投資や金融に詳しくない方、興味がない方にこそインデックスファンドを検討していただきたいと思います。
選択眼が無い方がインデックスファンドを選ぶべき理由
インデックスファンドは手数料が安い
インデックスファンドの年間コスト(信託報酬):0.1%~0.7%程度
平均的な投資信託の年間コスト(信託報酬):1.5%~2%程度
1%程度の違いがあります。これを上回る成果を上げ続けるのはとても困難と言われています。
資産運用の利益は以下の式で表すことができます。
資産運用の利益=
(A アセットクラスの収益)+(B 運用の上手下手)-(C コスト)
A アセットクラスの収益:マーケット全体の上げ下げ
B 運用の上手下手:良い商品かどうか
C コスト:手数料
式を見ればわかることですが、利益を大きくなるには、
- Aが大きくなる
- Bが大きくなる
- Cが小さくなる
のパターンがあります。Aはすべての人にとって同じですからBとCがカギになります。良い商品選びに自信がある方はBを重視した商品選びをすれば良いと思いますが、自信がない方はCのコストに着目した商品選びをした方が良いでしょう。
実は成績も良い
東証株価指数や日経平均に連動するのがインデックスファンドです。ところがデータを見てみると高い手数料を負担している多くの方がお持ちの投資信託と比べても成績に遜色がないケースが多いのも事実です。
「この商品どうですか?」と聞かれた際には運用レポートなどを確認しますが、経験的には、少なくとも半分以上の商品がインデックスファンドに負けています。1年単位でもそうですから5年、10年と投資期間が長くなるといっそうインデックスファンドが有利になると言われています。
当然ですが、インデックスファンドを上回る成績のファンドは年単位では半分弱はあるはずですし、10年という期間でもインデックスファンドを上回る成績を上げるファンドも2割程度はあるといわれています。ただし問題はそれを事前に知ることができない、という点なのです。
ですから、よほどの選択眼がある方や選択眼があるアドバイザーがいる方でなければインデックスファンドを選んだ方が、特に長期の視点では良い結果が望める可能性が高いと思います。
購入後の対処もシンプル
値上がりしているときは良いのですが、大きく値下がりしているときは基準価額の動きが気になりますよね。インデックスファンドであれば、マーケット全体の値動きに連動するのでチェックしなければならないのはマーケット全体の値動きだけです。
一方多くの方が保有しているアクティブファンドの場合には、値下がりの理由が
- マーケット全体によるものなのか
- 運用がうまくいかなくなったからなのか
- 運用がうまくいかなくなった理由は何なのか?
等々多くのことをチェックする必要が出てきます。一般の方が直接運用会社にアクセスしてこれらを確認することはできませんし、販売窓口もそこまでフォローをしきれないのが現実です。
投資信託を勧められた場合には、是非、「同じ投資対象のインデックスファンドやETFはないのですか?」、と聞いてみてはいかがでしょうか?